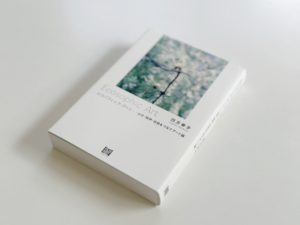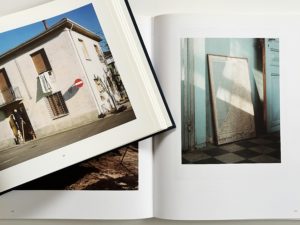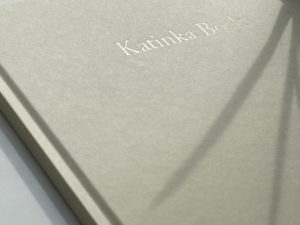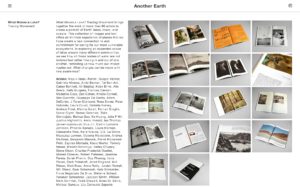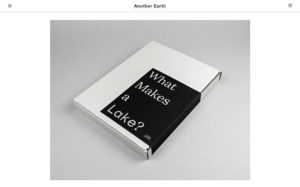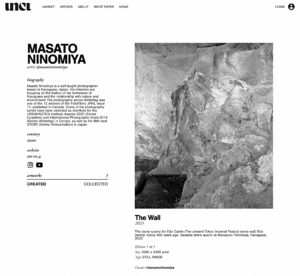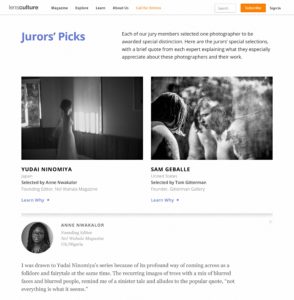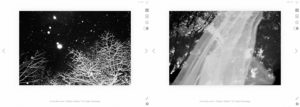Eitai Bridge | 1926 – Present | Hakozaki, Tokyo
2023年9月1日、関東大震災から百年。
2000年代の始めまでの約七年間、当時子会社から出向していた親会社は、今も東京箱崎の永代橋の袂に建つ外資系IT企業だった。つい先頃になって、両親宅で高齢の母から思いもよらぬことを聞いた。関東大震災のときに、難を逃れるために祖父が身ひとつで隅田川へ飛び込んだ場所は永代橋の袂だったと言う。箱崎周辺は故郷のように心落ち着く場所で、今も年に一度は永代橋に行き、隅田川を行き交う船と河岸に建つかつての勤務先ビルを眺める。永代橋から佃島のタワーマンション群や月島方面を眺めたときに左手に見える相生橋は、戦時中の難を逃れるために祖父が再び隅田川へ飛び込んだ場所らしい。いずれの橋も震災や戦火で倒壊し、のちに再建されている。高松から単身上京した父との馴れ初めの場所は駒形橋、と母は言った。

Left: Mother + A map of traditional areas of Tokyo along the Sumida River. Right: Komagata Bridge | 1927 – Present | Asakusa, Tokyo.
人種差別をしない人だったのよ、と母は祖父を回想していた。近所に暮らしていた台湾人や韓国人、その子供達を祖父は可愛がったらしい。その時代、祖父のような人は生きづらかったと思う。大震災の直後、旧日本軍によって朝鮮人虐殺事件が起きた。戦時中には国家の指針に沿わない反戦主義者も「アカ」と呼ばれて収監された。壺井栄『二十四の瞳』、江馬修『羊の怒る時』、髙橋健太郎さんの写真集『A RED HAT』などでそれを伺い知ることが出来る。なまじっか僕の社会人としての出発点は外資系だったので(所属部門のクライアントは常に国内企業で語学力は不問だった)年功序列や保守的思想よりも、個々にユニーク(独自性)であることを尊重するグローバルの価値観や祖父の思想に共感する。祖父はイキな人だったのかな?と僕は母に訊いた。イナセな人ね、と深川出身の母は佃節のように言った。粋な深川(芸者)、鯔背な神田(職人)、人の悪いは麹町(大名屋敷やお侍)。
ただでさえ歳をとったら不潔に見えるのだから、年齢を重ねたらパリッとした白いシャツを着た方がいい、と祖父は五十代で言ったらしい。なかなかに良いことを言うなと思った。その当時の祖父と同年代に差し掛かった自分が白シャツを着こなすのはそこそこ難しく感じるけれど、村上春樹の小説に登場するようなスタイリッシュな中年男を目指すのも悪くはないかもしれない。いずれにせよ体型維持を怠ってはどちらも難しいのだ。